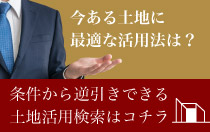土地活用におけるリースバック
土地活用におけるリースバックとは?
テナントなどが使用したい土地の地主に「建設協力金」を支払い、地主が土地に物件を建設。その建物を使ってテナントが事業を行なう契約方式をリースバックと呼びます。建設協力金方式とも呼ばれ、地主は借主から受け取ったお金を使って自分名義の建物を所有できるのが特徴。初めに投資するお金を抑えつつ、借地料よりも収益性のある建物賃料を得られます。
借主からもらった建設協力金は、毎月の賃料から差し引かれる形で返金されることが一般的。この返済の仕組みからリースバックと呼ばれているようです。
リースバックで土地活用する流れ
- 土地を利用したいという事業者から「建設協力金」として、無利息の建設代金を回収。事業者の希望通りに建物を建てたら、建物を一括賃貸します。
- 賃貸する際、無利息で借りている建設協力金は「保証金」に名目を変更。
- 土地所有者は月々の賃貸料を受け取り、賃料と相殺する形で保証金を返済していきます。
リースバックのメリット
土地活用のリスクを抑えられる
建設協力金によって不動産運用にかかる初期費用を抑えられるため、リスクを低減できます。高いお金を払って物件を建てたのに入居者がいなくて赤字、といった心配がありません。
途中解約の場合、保証金の返済義務がなくなる
建設協力金の返済は物件の借主から賃料をもらいながら返済できるので、負担がありません。途中解約になった場合、保証金の返済義務がなくなるので収入がないのにお金を払わなくはいけない状態にならないのが安心です。
リースバックのデメリット
建物が借主仕様なので転用しにくい
土地に建設する住宅は借主の希望に沿ったものになるため、途中解約になった場合転用がしにくくなる可能性があります。賃料を見直したいときに家賃交渉が難しいケースも。
建物が地主の所有物になるので税金の負担がある
借主である事業者が利用する建物は地主の所有物になるため、建物に課せられる固定資産税は地主の負担となります。リースバックは15~20年の契約期間が一般的。テナント撤退後は建物だけが残り、税金の負担が大きくなります。
事業用定期借地との違い
| リースバック | 事業用定期借地権方式 | |
|---|---|---|
| 建物の名義 | 地主 | 借主(事業者) |
| 賃借対象 | 建物 | 土地 |
| 賃貸期間終了後 |
建物が残る |
更地にして返還 |
リースパックと似ているものに、事業用定期借地権方式があります。これはあらかじめ契約で定めた期間だけ土地を貸す契約方式です。期間が終了したら、借主は地主に土地を返済する義務が発生します。テナント撤退後の税金負担がないのが利点。しかし、リースバックと違い「賃貸期間内は途中契約できない」「固定資産税の減税が受けられない」などの懸念点があります。
リースバックが使える土地活用の例
- コンビニ経営
- 福祉施設経営
- 駐車場経営
- アパート経営
- テナント経営
初期費用は少なめだけどリスクもある
リースバックの大きな魅力は初期費用を抑えて土地活用ができること。土地を利用する事業者が決まっている状態で物件を建てられるので、空室になるリスクもありません。
しかし、場合によっては返済金や税金が収入を上回ってしまったり、事業者側からの提案に合わせた複雑なキャッシュフローを考える必要があることも。
初期費用を抑えつつ土地活用ができる方法は他にもあるので、自分に合っている方法はどれなのかじっくり検討してみましょう。