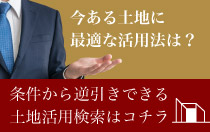損失を避けるために土地活用の失敗例を知る
土地活用と聞くとアパート経営や店舗貸出など、さまざまなケースをイメージするかと思います。そして、成功例を見聞きするため、今すぐ行動に移したいと考えている方もいるのではないでしょうか?しかし、土地活用には成功だけではなく、失敗するケースもありますし、簡単なビジネスではありません。
このページでは土地活用の失敗例をまとめました。土地活用の思わぬリスクや誤った認識を含めて紹介していきます。
土地活用の失敗例
土地活用を行う上で、「意味や目的をはっきりせず活用を始める」ことは失敗の可能性を高める原因のひとつ。また、コストを抑えすぎると、利便性や収益に影響を与えるため注意が必要です。それでは土地活用の失敗例をいくつか紹介していきます。
1.土地活用の仕組みを理解しないままま運用を開始する
そもそも土地活用の意味や仕組みをよく理解しておらず、単にアパートやマンション経営だと思い込んでいるケースもあります。そのため、アパート経営以外の方法で活用した方が収益を得やすいケースにもかかわらず、気付かずアパートを建てて失敗を招いてしまう方も存在します。
だからこそ、土地活用の仕組みを知ることが大切なのです。土地活用は、ある土地や建物の家主となって、第三者に土地や建物を貸すことを指します。つまり、土地の形状や敷地面積、建物の種類に関して特に区分されていません。たとえばオフィスビルを建てても構いませんし、保育所や介護施設、ライブハウスなどどのような用途にも活用できます。
また、とりあえずアパートやマンションといった建物を建てるのではなく、その土地と周辺環境に合った建物を建てて運用する必要があります。オフィスビルが多数建てられている場所に、小さなオフィスビルを建てても何らかの工夫をしなければ集客は難しいところです。
これから土地活用を始めようと考えている方は、自身の所有している土地がどのような用途の建物や施設に向いているのか確認したりプランを立てたりすることから始めましょう。しかし、個人で周辺環境の調査や収益率の計算、建築費用など容易ではありません。
実際にプランを立てたり周辺環境の調査などを始めたりする際には、ハウスメーカーへ相談するのが大切です。
ハウスメーカーは住宅やアパートの建設だけでなく、土地に合った運用方法や建築費、予想収益率などプロ(1級建築士など)の視点から調査・提案してくれます。
2.需要を考えずに間取りを決めてしまう
一戸建てやアパートなど住居を建てる場合、住居系の土地活用では、間取りが重要なポイントです。需要や土地の形状などを考慮せず、間取りを決めてしまうと空室のリスクも高くなってしまいます。
間取りから見た需要はワンルームが高く、次いで2DKや3DKという順番です。特に間取りが広くなっていくほど、需要も下がっていく傾向のため、3DKや4DKの部屋ばかり建ててしまうのは一般的にハイリスクといえるでしょう。
間取りの方針を決める時は、まずハウスメーカーへ相談し、周辺の需要や求められている間取りなどを確認した上で計画的にプロジェクトを進めていきましょう。
3.何となくサブリースを選択し失敗
土地活用では、専門用語が多数出てきます。そして、人によっては「サブリース」と呼ばれる契約方式の意味を調べず、何となく契約を進めて失敗してしまいます。
サブリースとは一括借り上げのことで、土地と建物を借り上げてもらいサブリース会社側と入居者が転貸借契約を結びます。そしてサブリース契約では、通常の貸借契約と違い空室率に関わらず、毎月の一定の賃料を支払ってくれます。
ただし、空室率が増えると段階的に賃料を下げられてしまうことも。また、満室状態でも、賃料は満額支払ってもらえません。
このようにサブリースは、収益性という点でデメリットのある契約方式です。担当者からサブリースを勧められたとしても安易に選択せず、自己資金と借入金で建物を建てる運用方式を検討してみるのも大切です。
4.とにかく低コストの土地活用に重視過ぎた
人によっては、土地活用のために必要なコストをとにかく抑えようと考えるかと思います。確かに建築費用など抑えることができれば、負担も少なく済みます。しかし、無理に建築費用を抑えてしまったことで、建物および部屋の品質に影響を与えてしまう可能性もあり要注意です。
さらに集客および空室率増加のリスクにもつながります。土地活用では、必要以上のコストをかけないと同時に、顧客=入居者(借主)に対して利用しやすい建物作りにも力を入れなければいけません。
まずは建築費用の抑えすぎによるハイリスクな側面もあることを理解しておきましょう。たとえばハウスメーカーへ適正な建築費用と間取り、コストを削るべきではないポイントを確認しておくのもおすすめです。
5.容積率を重視し過ぎて住みにくい間取りとなった
土地活用における失敗例では、容積率にこだわりすぎて利回りの低下につながるケースも存在します。
そもそも容積率は、「敷地面積(土地全体の面積)に対する、延床面積(建物各階の面積)の割合を示した指標」です。そして容積率は、各地域によって200%など数値が定められています。
仮に容積率の上限が300%で、250%や280%といった数値になるよう建物を建てた場合、その土地で認められている貸借面積を余すことなく使用しているといえるでしょう。
ただし、容積率の未重視していると、思わぬミスにつながります。それは、利便性の低下による空室率増加リスクです。
たとえば容積率を上限いっぱいまで使い切るために、5階建てや7階建てなど縦方向に伸ばして建築するとします。階数が増えることは、階段だけでなくエレベーターも必要となります。そして、エレベーターを設置するために部屋数や1部屋当たりの面積を減らさなければいけません。
このように無理な間取りは、建物の品質低下や住みにくさにつながり収益率も下がってしまいます。また、エレベーターの定期的な保守点検費用もかかるため、維持費用コストもかさみます。
土地活用を行う時は、容積率だけでなく1部屋あたりの面積と住みやすさ、維持費用コストなど多角的な視点から計画を立てましょう。
6.一棟貸しで借主の選定が甘かった
一棟貸しをする際には、借主の選定にも気を付けなければいけません。
まず一棟貸しとは、建物一棟ごと事業者へ貸し出す運用方式のことです。たとえば、一棟を介護事業者へ貸し出して、福祉施設として運用してもらい賃料を毎月支払ってもらうといった仕組みです。
アパートやマンションといった住居向けの運用と違い、1つの事業者が事業目的で利用するため、退去しなければ毎月の賃料も安定しやすいといったメリットもあります。つまり裏を返せば、すぐに退去されてしまうと毎月の収益も急激に下がってしまうのです。
一棟貸しのリスクを少しでも抑えるためには、借主となる事業者の経営状況や過去の実績を確認した上で慎重に選定しなければいけません。しかし、失敗例の中には経営状況などを確認せず、高い賃料を支払ってくれる事業者と契約してしまい、後から経営悪化が表面化して退去となるケースもあるようです。
高い賃料を支払ってくれる事業者の中には、とにかく早く出店するために無理をしている可能性もあります。経営状況の把握は難しいものの、過去の実績(店舗数や売り上げなど)は公式サイトなどから確認できます。
7.低コストを重視し過ぎて利便性の低い間取りとなった
商用店舗やオフィス向けの土地活用を行う際、建築費用をとにかく抑えようと軽量鉄骨を選択してしまい、利便性の低い間取りとなってしまうケースもあります。軽量鉄骨では多数の柱が必要となるため、間取りの制限が増えてしまいます。住居用であれば軽量鉄骨でも大きな問題はありません。
ですが、商用施設やオフィス向けの間取りは、フロア内に柱を設置しないのがセオリー。理由は単純で、仕事に必要な物品や設備を設置できない空間も出てきますし、レイアウトが制限されるためです。
軽量鉄骨造りの構造は、重量鉄骨と比較して建築費用を抑えられます。しかし、梁や柱が細くなるため、構造上柱の本数を増やさなければいけません。
対して重量鉄骨造りでは、フロア内に柱を入れない無柱空間で建築可能です。店舗やオフィス向けに貸し出す場合は、建築費も考えながら無柱空間など利便性にも配慮しましょう。
8.店舗区画を2階以上にも設けてしまう
住居用マンションの中には、1階部分を店舗として貸し出しているケースもあります。そして、2階以上の区画も店舗として貸し出しているケースの多くは、テナント誘致に失敗しています。
駅に近い土地など立地条件の良い場所で土地活用を行う際は、上層階を住居・1階部分を店舗として貸し出すことで賃料単価の高さなどでメリットを得られます。また、この戦略自体には問題ありません。
ただし、2階以上の区画は客足が少ない傾向のため、事業者側も出店しない傾向にあります。原則店舗の出店は、1階部分にのみに絞ることもひとつのリスクヘッジになり得るでしょう。
9.一棟貸し後に資産区分があいまいになってしまう
一棟貸しの中には、借主との資産区分や退去時の原状回復に関するトラブルが発生することもあります。
一棟貸しでは、建物の着工前にテナント(出店企業)が決まり、テナントと打ち合わせをしながら間取りなどを決めていきます。そして、建物の資産区分については、オーナーと施工会社で締結した範囲となります。
たとえば施工後にテナント側が、看板や電飾看板、窓ガラスに貼るサービス名などを示すステッカーなどを自費で追加した場合、その部分についてはテナントの資産として区分されます。
特にトラブルとなる原因の1つが、建物内の内装などをテナント側で追加・修正を繰り返し、いつしかどの部分がオーナー・テナントの資産か区別できない状態になってしまうケースです。
たとえば災害などで内装が損壊した場合、どの部分の修繕費用をオーナーが負担するのか分かりません。さらにテナントが退去する際、原状回復工事の費用もどこまでがオーナー側の資産なのか分かりにくいトラブルも考えられます。
トラブル防止策として一棟貸しの場合は、テナント側で行った工事箇所や資産の種類など、書面で一つひとつ残しておきましょう。
10.フルローンで建てたため返済額が大きく経営が厳しい
フルローンとは、物件価格の全てを借入額でまかなう方法のことです。購入時の自己負担を軽減できる一方、空室時の返済負担が相対的に増加したり、売却時しようとしても売却価格よりも借入残高が多く売却できないといった失敗につながるリスクもあります。
入居者の退去は、いつ起こるか分かりません。建物自体に原因がある場合もあれば、入居者の都合による退去も十分に考えられます。そのため土地活用では、空室も想定した上で資金管理を行う必要があります。
そこでフルローンを選択してしまうと自己資金を含む借り入れや100%自己資金のケースと違い、毎月の返済額は大きい状態です。
空室率の高い時期になると返済できない状態に陥ってしまうリスクもあるため、フルローンは可能な限り避けましょう。物件価格の少なくとも30%程度は、自己資金で負担できる状態にしておくのも重要です。
土地活用の失敗例から学べること
これから土地活用を始める時は、基礎知識を身に付けた上でハウスメーカーへ相談するのが大切です。
他にも以下のような点を押さえておくのも重要です。
- コストを適切に抑える:重量鉄骨造りなど必要な部分には投資を惜しまないこと
- 契約内容など基本要素は理解しておく:サブリースのリスクや資産区分など
- 自己資金は全費用の30%以上は用意しておく:フルローンはハイリスク
- 需要を理解する:需要のある間取りや2階以上にテナントを誘致しないなど
土地活用の成功例と失敗例どちらも確認し、不動産経営に関して何が不足しているのか、どのような行動がハイリスクなのか理解した上で準備を進めましょう。